第八話 青年インカ(8)
その頃、トゥパク・アマルたち家族4人は、トゥパク・アマル自身の牢に戻っていた。
トゥパク・アマルは、己の牢内で、既に堀り上げて開通させていた土壁からアドベ(日干しレンガ)を抜き取り、そこを潜り抜けるよう他の3人に促す。
「さあ、急いで、ここを!!」
抜け穴の向こうは暗闇で視界が利かないが、1メートル幅ほどの足場を隔てて、その向こうには水の流れる音がする。

「ここは!…――地下水路が通っているのね」
麗しい目元を細めて振り返る、さすがに察しの良いミカエラに、トゥパク・アマルは頷いた。
「まずは、水路伝いに、水路の脇の足場を走る。
その後のことは、進みながらだ。
さあ、皆、急げ!!」
大人一人が這うようにして何とか抜けられる程度の狭い穴だが、ミカエラや息子たちが身を屈めて素早く潜(くぐ)り抜けるうちにも、トゥパク・アマルは手早く別の作業を進める。
彼は、寝台の背もたれ部分を成していた高さ50センチほどの細長い円筒状の木片を、豪腕で強引にへし折ると、擦り切れたシーツを引きちぎって巻きつけ、火をつけて、たちまち即席の松明(たいまつ)を作り上げた。
松明を仕上げると己自身も土壁の抜け穴を潜り抜け、抜けた穴に、敏捷にアドベを並べ直して、そこを塞いだ。
…――とはいえ、脱獄したと知れれば、このような穴は、いとも簡単に見つけられてしまうであろう。
トゥパク・アマルは、片腕に松明を掲げたまま、再び、フェルナンドを高々ともう片腕で抱き上げる。
それから、今、息遣いさえも感じられるほどに直近にいるミカエラとイポーリトを、真っ直ぐに見つめた。
闇を照らす松明を握る指先に、無意識のうちに、力がこもる。
(ここまできて、再び囚われるわけには、絶対にいかぬ…!)
トゥパク・アマルは、鋭い目で懐中時計に視線を走らせた。
間もなく、次の巡回時間である。
開錠した牢には施錠をし直してきたが、牢内に彼らがいないことが分かれば、すぐに追っ手が迫ってくるはず。
トゥパク・アマルは、長男イポーリトに松明を差し出す。
「イポーリト、そなたが先頭に立ち、それを持って水路の脇を全速力で走れ。
さあ!!」
イポーリトは燃え上がる松明をガッチリと受け取ると、「はい!!」と、若者らしい溌剌とした返事を返して、勢いよく水路脇の足場を走りはじめた。
岩状の足場とは言え、その空間全体の湿度が異様に高く、足場自体も水気を含んで滑(ぬめ)って苔むし、一寸でも油断すれば足を滑らせてしまいそうだ。
それでも、松明で周囲を照らしながら、拷問の後遺症のために足を引き摺りながらも敏捷に走る若いイポーリトのすぐ後方を、やはり足を引き摺りつつも、なお、俊足のミカエラが続き、トゥパク・アマル自身は高熱のフェルナンドを腕に抱き上げたまま、その後に続く。

松明の眩しさと、苔や泥を跳ね上げながら走り来る突然の騒然たる来訪者たちに、驚愕した無数のドブネズミたちが、群れを成して一斉に水際から飛び出してきた。
その数たるや、普通の感覚では、卒倒しそうな軍団ぶりである。
が、そのようなネズミの群れなどものともせぬミカエラが、険しいほどに凛とした表情で、己のすぐ後方を走るトゥパク・アマルを振り向いた。
「もうそろそろ、牢では、私たちのいないことに気づいて大騒ぎになっている頃ね?
このまま水路沿いを走っていても、程なく見つかってしまうわ。
それに、私たちが地下水路に逃げたと分かれば、すぐに敵は水路の出口にも回るはず」
トゥパク・アマルは、鋭利な横顔で頷く。
「その通りだ。
だから、この水路から、さっさと抜け出さねばならぬ」
「水路から抜けるって、どうやって?!」
「案ずるな。
手は打ってある」
トゥパク・アマルは疾走しながら、少し声を大きくして、皆に聞こえるように言う。
「ミカエラ、イポーリト、そして、フェルナンドも、周りの音によく気を付けていておくれ。
人の叫び声のようなものが、水路伝いの壁から聞こえないか」
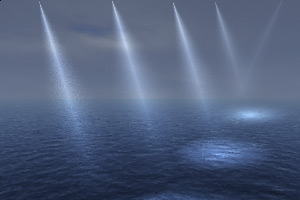
前方に視線を戻していたミカエラが、再び、決然と振り向いた。
「あなた…――?
人の叫び声ですって?
こんな地下深くに…?!」
このような場所で、一体、何を言っているの?と、半ば憮然とするほどに勝気な目を瞬かせる妻に、トゥパク・アマルは悪戯っぽく微笑んだ。
「説明は後だ。
さあ、わたしの言ったようにしてくれ。
急いで!!」
ミカエラは、今一度、首を傾(かし)げて、意味不明な夫を鋭く一瞥した。
が、彼の首に巻きつくようにして安心しきった笑顔を見せている幼いフェルナンドに視線が止まると、女神のような柔和な眼差しになって、「分かったわ」と、前方に向き直った。
と思いきや、フェルナンドが、まだ少女のような澄んだ声で、「人の叫び声がする!!」と、声を上げた。
え!――と、見下ろすトゥパク・アマルの腕の中で、フェルナンドが繰り返す。
「父上!
後ろの方から、人の叫び声!!」
ミカエラは、咄嗟にトゥパク・アマルを振り返った。
「それって…!!」
「!!…――それは、追っ手だ!
イポーリト!
火を消すのだ。
水に入れろ!」
「はい!!」
松明を掲げながら先頭を切って走っていたイポーリトが、素早く水路の中に火を突っ込んで消す。
突如、辺りは、完全なる濃厚な闇に包まれた。
「さあ!
走れ!!
まだ追っ手は遠い。
諦めずに、全力で走るのだ!!」
トゥパク・アマルが声を低めつつも、しかと力を込めて皆を激励する。
彼はフェルナンドを抱き上げたまま先頭に立って、闇に目を凝らしながら、他の二人を誘導するように疾走する。
さすがに戦士さながらに運動神経も優れた長身のミカエラは、相変わらずの俊足で、また、二人の息子たるイポーリトも、その若さも手伝って、両親を凌ぐほどの瞬速で駆け抜ける。
とはいえ、3人共、拷問の後遺症の癒えぬ身…――どれほど、渾身の力で走っても、限りはあった。
他方、背後からは、鬼のような剣幕で獲物を狩り出すように追ってくる白い役人たちが、猛り狂って叫ぶ罵声――彼らの執拗な恐るべき執念の炎は、インカ帝国侵略時以来、この反乱期を通じても、これまで散々に見せつけられ、挙句、無残にも、その炎に繰り返し焼け出されてきたのだ。

此度、また同じ苦渋を舐めるわけには、絶対に、いかない――!!
アンデスの深山を走る聖獣ピューマのごとくに、いっそう加速しながらも、それら白人たちの怒声の中にアレッチェのものも混ざっていることを、トゥパク・アマルは敏感に聞き分ける。
(アレッチェ…――もう、ここに?!
脱獄が、今宵と勘付いていたのか……?!)
さすがのトゥパク・アマルの横顔にも、これまで以上の緊迫感がよぎっていった。
早くも、あのアレッチェが追っ手に混ざっているとなると、形勢は決して、自分たちに甘くは無いだろう。
フェルナンドを抱いて走るトゥパク・アマルの俊足に、さらなる加速がかかる。
ミカエラやイポーリトも、それに続いた。
その間にも、白人たちの常軌を逸した獰猛な怒声と罵声が、狂気を孕むスピードで、背後から着実に迫り来る。
その直後、背後から銃声……―――!!
「!!――伏せろ!!
水中へ!!」
トゥパク・アマルの声より速く、4人は反射的に水中に飛び込み、身を伏せた。
さすがに、まだ距離があるためか銃弾は届かぬが、水路の方々から、銃声に怯えたドブネズミたちが、狂ったように、巨大な影さながらの大群をなして走り去った。
「撃ってきたか」
「ええ。
本気で、ここで殺す気かもね」
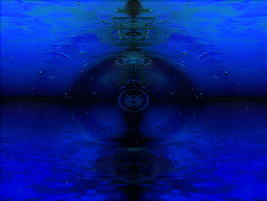
トゥパク・アマルは、水深1.5メートル程の水中で、フェルナンドを強く己の体の内側に抱き入れた。
そして、ミカエラとイポーリトも水から上がらぬよう制しながら、低く言う。
「このまま水中に身を置き、水面ぎりぎりに身を屈めて進むのだ。
敵も闇の中での目くら撃ち――むしろ、我々を心理的に追い込もうとの算段であろう」
「!…――父上!!」
トゥパク・アマルの言葉を遮って、急に、イポーリトが凛とした鋭い声を上げた。
「イポーリト?」
「父上!!
人の叫び声がする!
後ろじゃなくって、前の方から!!」
「!」
4人は咄嗟に息を詰めて、全神経を集中させて前方の音に耳を欹(そばだ)てた。
その時、何かを隔てたような向こうから、微かに4人の耳に聞こえ来る声―――!!
『た…す…けて…くれ――…――!』
「!!!」
皆、暗闇の中に慣れてきた目を大きく見開き、言葉も失ったまま、互いの顔を見合わせた。
確かに、どこからか、人の微かな叫び声が聞こえるではないか!
「あ…なた?
本当に!?
い…一体、誰が、こんなところに?!」
ずぶ濡れになりながらも、女神像のような綺麗な目元を今は張り裂けるほどに大きく見開いて、平素は沈着なはずのミカエラも、混乱と驚愕とで素っ頓狂な声を上げている。
一方、トゥパク・アマルは、抱いていたフェルナンドをミカエラにしっかりと預けた。
「子どもたちを頼む…!」
そして、己自身は水から飛び出し、足場へ上がると、声のした方向の壁際へと駆け寄った。
驚いている3人が水中から何か言おうとするのを、「シッ!」と、鋭く制する。
彼は、壁際に耳を当てながら、這うように移動していく。
その間にも、壁を隔てたようなどこからか、微かな人の声がする。
『たす…けてくれ…!
開けて…くれ……』
「ここか!!」
トゥパク・アマルが壁際の一箇所で歓喜を滲ませた声を上げた瞬間、再び、背後から銃声――!!
伏せろ!!―――ミカエラと息子たちは反射的に水中に身を沈め、トゥパク・アマルも、銃弾を避けるように、咄嗟に壁に全身を寄せた。
まだ弾は届かぬが、銃声も、背後の人の怒声も、けたたましい追跡の足音も、先程より確実に近づいている。
トゥパク・アマルの手助けをしようと、ミカエラが、水路際に移動するようにして僅かに水中で動いた。
「そなたたちは、そのまま水中にいなさい!!」
さすがのトゥパク・アマルも、語気荒く言い放つ。

それから、己自身は声の聞こえた壁周辺の方々に両腕を広げて張り付くようにしながら、懸命に何かを動かすような動作を続けている。
その横顔には水滴と共に幾筋もの汗が伝い、切れ長の目は険しく吊り上がり、目元が引きつるように痙攣している。
息子たちを抱き寄せながら水面から頭だけ出して見守るミカエラの目には、夫のこれほど必死な表情は見たことがなかった。
相変わらず、壁向こうの方からは、確かに、男の声で、『助けてくれ!出して…くれ!』と、途切れ途切れに聞こえ続けている。
しかし、背後からは、さらに迫り来る追っ手たち―――!!!
さすがのミカエラの心臓も、早鐘のように打ち鳴っていた。
怒涛のような事態の展開に、すっかり忘れていた身を切るような水の冷たさが、急激に骨の髄まで染みてくる。
(もはや…――ここまで……?)
彼女は、震えるように身を固めながら息を詰めている二人の息子たちの肩を、ギュッと強く抱き寄せた。
その時だった。
トゥパク・アマルの腕が、壁の一部をガラガラと鈍い音と共に押し開けていくさまがミカエラの目に、はっきりと映る。

「!!――え!?」
「さあ!!
中へ!!」
ミカエラや息子たちが呆然と驚愕の眼を見開く間にも、トゥパク・アマルの強靭な腕は、3人を次々と掴み上げると、壁面に突如現れた穴のような中に、全員を容赦無く投げ入れた。
そして、己自身も、最後にその中に飛び込むと、次の瞬間には、猛烈な勢いで壁に開いた穴の入り口をガラガラと閉じていく。
たちまち、その巨大な一枚岩のような入り口が、ガタンッ!!――と重々しい音と共に、完全に閉じられた。


